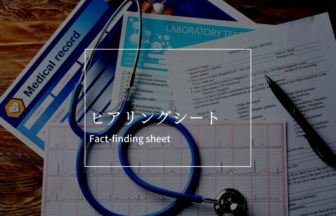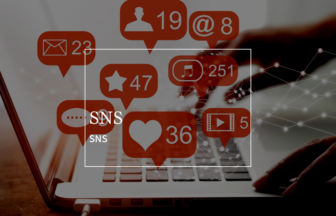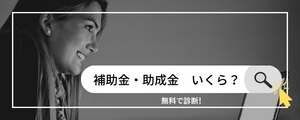オウンドメディアとは、企業が、見込み客集めに適したコンテンツ、例えば業務ノウハウや事例などを配信するWebサイトのこと。(主にWeb上に構築したメディアを指していうが、広義には企業が展開するアナログ媒体も含む)
|売りかた大全集
オウンドメディアの概要
ターゲット層が知りたそうな話題について、50〜200本ほどのWeb記事・動画を発信し、それによりSEO(検索エンジン最適化)による集客をねらいます。はやい話が、ググって上の方にくるWebサイトにすることで、見込み客から見つかりやすくする、ということです。
一般的には、自社商品・サービスに関連する内容(使いかた・ノウハウ・事例・開発秘話・隣接商品の情報・ほかとの比較など)についてコンテンツを制作します。
広告ではないため、料金はかからないのに、SEOによって上位表示されるとたくさんの訪問者を得ることができます、という点が最大のポイントです。また、読み手からすると、上位表示記事は信頼性の高いものとして認識されます。
内容については、必ずこれでないといけないというものはありませんが、1つのページごとに、読み手にとってほしい行動を明確化しておく必要はあります。検索によりオウンドメディアの記事を読みに来るわけですから、何かしらの興味や必要性がある見込み客です。
「更に詳しい情報を受け取りたい場合はメルマガにご登録ください」「この商品にご興味がある方はぜひお問合せください」といった形の、ストレートな表現で構いません。しっかり明記しておきましょう。
オウンドメディアを導入すべきなのは
オウンドメディアは、直感的には効果・効能がわかりにくい商品・サービスについて、特に有効です。そうした商品・サービスでは、一般に、顧客のリテラシー(業界・業務・専門用語などの知識)を高めなければ販売しにくい、という特性があるためです。顧客教育(ナーチャリング)という表現もされます。
オウンドメディアは、多くは見込み客が能動的に検索をした結果たどり着くものです。そうした検索需要に対し、的確に答えを返してくれた記事と書き手には、少なからず「先生」としての好感を覚えるでしょう。
記事数がある程度必要だという話をすると、「うちのような中小企業にはそんなノウハウなんてない」と言われますが、まったくそんなことはありません。むしろ、ニッチな業界、地域性のある業界、単一商材だけで展開してきた業界の中小企業こそノウハウの宝庫です。
アイディアの出し方は、下の「オウンドメディア導入の5ステップ」に添付してありますので、ぜひ一度ご検討ください。
オウンドメディアの成功ポイント
オウンドメディア導入の際は以下の点にご留意いただくと、成果が出やすいです。
①スタート時より、リライト(改良)を重視する:立派な記事を書こうとしても、いきなりはムリです。それよりも、まずはメディアとして成立するコンテンツ数30〜50程度を揃えてさっさと公開しましょう。公開したばかりのオウンドメディアにいきなり読者が殺到することは、まずありません。3ヶ月くらい放置しておくと、反応が良い記事(表示順位が高い・表示数が多い・滞在時間が長い)が出てきますので、その記事を1〜3位に表示されるように改良を加えます。
②コンテンツづくりには社内勉強会を利用する:ノウハウをはじめ、来訪者を惹きつけるコンテンツづくりのために、まずは社内勉強会を開催していただくことを推奨しています。ペースは週1,2で結構です。勉強会でとりあげたテーマそのものでもいいし、脱線して盛り上がった話題でもOKです。それらは、少なからずプロである社員が知りたいこと、興味を持っていることなので、あなたの会社の見込み客が関心をもっているケースが多いです。
③どんな役割を担わせるかを決める:マーケティング全体を俯瞰してみたときに、このオウンドメディアはどんな位置づけなのか、を明確にします。あれもこれもは出来ません。オウンドメディアから商品購入ページに直行してほしいのか、それとも、資料請求をうながして顧客リストを集めるのか、既存顧客に商品の使いかたをレクチャーしてLTV(顧客生涯価値)を伸ばしたいのか、などです。
④どんな行動をとってほしいかを分かりやすくする:上記③に対応して、オウンドメディアの各ページに、この記事を読み終わったら(または途中でも)何をしてほしいのかを明示しておきます。そうすることで、ゴール率の高いページとそうでないページが分かり、改善の手が打ちやすくなります。
⑤広告を併用する:「え、無料って言ってたじゃん」と言いたいかもしれませんが、早期に立ち上げたい場合は、最初はリスティング広告(検索広告)やメルマガ広告を併用することをオススメします。なぜかというと、記事は読まれないと上位表示されないからです。最初の勢いづけだと思ってください。
オウンドメディアをほかの売りかたと比較
オウンドメディアを、よく比較される売りかたと並べてチェックしてみましょう。
(作成中です。もうしばらくお待ち下さい)
オウンドメディアの導入・運用・改善にあたっての注意点
オウンドメディアでは、以下の点にご注意ください。
①SEO対策のコトバに踊らされない:SEO(検索エンジン最適化)にハマり過ぎないようにしてください。小手先の技術よりも、内容の濃さ・オリジナリティがある方が集客に結びつきます。ひまつぶしの10人がボヤーっと流し読む程度の形だけ整った総花的な記事を書くくらいなら、「こんなマニアックな記事、誰が読むんだろう?」と思うような記事を一生懸命スミからスミまで読んでくれる、たった1人を思い浮かべて書いてください。
②3ヶ月は数字を見ない:はじまったら、すぐに来訪者や検索順位が気になるところですが、少なくとも3ヶ月は、数字を気にする余裕があればひたすら記事を書きます。
③30位以下の記事はなおさない:順位が低い記事ほど手直しをしたくなりますが、時間のムダです。劇的に改善させることを狙うなら、同じテーマで構成を変えて新しく書いた方がまだいいです。リライト対象は、4位〜20位までの記事にしておきましょう。
④記事同士のつながりは考えない:「このページの次にこのページに」など動線をあれこれ考えても、訪問者はその通りには動きません。極端にいうと、最初は記事から記事への回遊を狙う必要すらありません。各ページごとに、「◯◯なお困りごとを持ってこのページに来たら、解決して帰ってもらえるか?」という、商売では当たり前の視点が大事です。それらを集めたオウンドメディアこそ価値があります。
オウンドメディアの導入5ステップ
step.1 ゴール設定をする
オウンドメディアが担う役割と、それについて①来訪者にとってもらう行動②その1年後程度までの目標を設定します。[メルマガ登録を集める役割→①来訪者にはメルマガ登録をしてもらう→②1年後に1,000リストを集める]などです。
step.2 予算と始期を決める
構築後は無料のオウンドメディアですが、つくる上ではCMS(コンテンツマネジメントシステム)の代金をはじめ制作料や人的工数、必要に応じて記事の外注代金もかかります。いつリリースしたいかなどと併せて考えてください。
step.3 実際のページをつくる
実際のページをつくります。コンテンツの内容については、下にアイディア出しのためのフォーマットを用意していますので、ご活用ください。50コンテンツに対し、おおよそ200案は必要になります。
step.4 公開する
いよいよ公開です。通常は、普通に検索してすぐ上位表示されることはありません。他の媒体(メルマガ、SNS等)を持っているならリンクを貼ってアピールします。また、地道ですが、メールの署名欄や名刺に記載しておくことも有効です。
step.5 効果検証と改善を繰り返す
公開して6ヶ月後を目処にリライト(改良)サイクルに入ります。よく設定される指標としては、[平均検索順位・PV(総閲覧数)・CV(移行率)]などがあります。
おまけ.スベらないダンドリシート
お役立てください。
<作成中です>
プロが使っている、もっと詳しいフォーマットも利用いただけます
(外部リンクです。遷移先から取得してください)
オウンドメディアに関してよくあるご質問
| Q.コンテンツを考えるヒントはありますか? |
|---|
| A.自社の商品・サービスが検索されそうなキーワードは、Googleの予測のほか、キーワードツールが複数存在します。検索時は2〜3個のキーワードを入れることが多いので「オウンドメディア 予算」といった複数語の需要に答えるコンテンツを考えていきます。 |
| Q.用語が難しいのですが |
|---|
| A.はい。略称・横文字はなんとかしてほしいものです。以下によく使われる用語の意味をこちらに列挙してありますので、ご参考にしてみてください。 略語・カタカナ用語一覧 |
| Q.記事を書ける社員がいないのですが |
|---|
| A.書いているうちに上達します。どうしても文章力に難ありなどの場合であれば、勉強会や社長の発言などを録音しておいて文字起こしを外注に依頼→さっと概要だけまとめる→ライターを外注という手段もあります。 |
| Q.効果の測り方が分からないのですが |
|---|
| A.ツールという意味では、まずはGoogle Analytics・Google Search Consoleを連携させてください。 |
オウンドメディアについて、コンシェルジュに相談する
ちょっとしたギモンから、本格的な検討まで、お気軽にご相談ください。